「家計の見直しって何から始めればいいの?」
結婚前の私も同じ疑問を抱いていました。同棲時代からお互いの収支は把握していたものの、いざ結婚となると「本当にこの家計で大丈夫?」という不安が。そこで結婚を機に家計を徹底的に見直した結果、年間20万円以上の固定費削減を達成しました。
ITコンサルタントとして働く私と妻、現在は2児の父として家計管理を続けています。「構造化思考」を家計管理に応用し、夫婦で協力して無駄を削減してきた実体験を、具体的な5つのステップでお伝えします。
家計見直しのきっかけと成果
結婚がもたらした家計改革
結婚のタイミングで、それまで「何となく」管理していた家計を本格的に見直すことにしました。同棲時代からお互いの給与や支出はある程度把握していましたが、細かい支出まで完全に透明化したのは結婚が初めてです。
見直し前の状況:
- お互いの固定費を完全には把握していない
- 使っていないサブスクの存在
- 「大手だから安心」で選んだサービス
- 何となく続けている保険契約
1年間で達成した削減効果
主な削減内容:
- 通信費: 月6,000円削減(年間72,000円)
- 保険料: 月5,000円削減(年間60,000円)
- サブスク: 月3,000円削減(年間36,000円)
- 無駄遣い: 月5,000円削減(年間60,000円)
合計:年間約23万円の削減達成
こんな人におすすめ
- 結婚・出産で家計を見直したい
- 固定費削減の具体的な方法を知りたい
- 夫婦で協力した家計管理を実践したい
- 削減した分を投資に回したい
【ステップ1】家計の完全透明化で基盤作り
クレジットカード家族カード戦略
最初に取り組んだのが、支出の一元化です。
実施したこと:
- メインのクレジットカードで家族カードを作成
- 基本的にすべての支払いを家族カードに集約
- 現金支払いは最小限に抑制
効果:
- 一つの明細で家計全体の支出が把握可能
- お互いが何に使ったかが完全に見える化
- 無意識の無駄遣いが自然に減少
「見える化」が生む心理的効果
支出が完全に見える環境になったことで、お互いが使ったものはすべて相手に見られるという意識が働きます。これが想像以上に効果的でした。
「これ買って大丈夫かな?」と一瞬考える習慣がつき、本当に必要なもの以外の購入が自然に減少。年間約6万円の無駄遣い削減につながりました。
【ステップ2】格安SIMで通信費を大幅カット
大手キャリアからの脱却
変更前:
- 夫婦ともに大手キャリア使用
- 月額合計約12,000円(2人分)
変更後:
- 格安SIMに変更
- 月額合計約6,000円(2人分)
年間削減額:72,000円
格安SIM移行の実際のプロセス
選定基準:
- 通信品質の安定性
- 料金の透明性
- 家族割の有無
- 手続きの簡便性
リモートワークが中心の私にとって、通信の安定性は重要でした。しかし実際に使ってみると、日常使いで大手キャリアとの差はほとんど感じません。
注意したポイント:
- 乗り換えタイミングの調整(違約金回避)
- データ使用量の事前確認
- 妻の理解と協力を得ること
【ステップ3】保険の見直しで無駄を排除
医療保険解約の決断
解約した保険:
- 医療保険(月額5,000円)
解約理由:
- 高額療養費制度で十分カバー可能
- 貯蓄で対応できる範囲の保障内容
- 保険料に対する保障の効率性が低い
年間削減額:60,000円
貯蓄型生命保険は継続の理由
一方で、貯蓄型生命保険は継続しています。効率性の観点では最適ではありませんが、妻の投資に対する心理的なハードルを考慮した戦略的な判断です。
継続理由:
- 妻が当初投資に否定的だった
- 貯蓄型なら「保険」としてマイナスイメージなし
- 実際は投資信託+生命保険の商品構成
- 妻の投資への第一歩として機能
現在では妻も投資に理解を示すようになり、NISAも併用しています。
【ステップ4】サブスク整理で隠れた無駄を発見
家族カード明細で見えた無駄
支出を一元化したことで、お互いが契約していたサブスクの重複や使っていないサービスが明らかになりました。
解約したサブスク:
- 重複していた動画配信サービス
- 使わなくなったアプリの有料版
- 忘れていた雑誌の定期購読
- 一時的に使った学習サービス
月額削減:約3,000円(年間36,000円)
サブスク管理の新ルール
導入したルール:
- 新規サブスク契約時は必ず相談
- 3ヶ月使わなかったら即解約
- 年1回のサブスク棚卸を実施
このルールにより、現在も無駄なサブスクの蓄積を防げています。
【ステップ5】データ分析で継続的改善
生成AI・BIツールを活用した家計分析
ITコンサルタントのスキルを家計管理にも応用。クレジットカードの利用明細をCSVでダウンロードし、生成AIやBIツールで分析しています。
分析のタイミング:
- 子どもが生まれた時
- 転職した時
- 引越しした時
- 年末の定期見直し
分析内容:
- カテゴリー別支出の推移
- 前年同期比での増減分析
- 無駄遣いパターンの特定
- 予算と実績の比較
夫婦での見直しプロセス
見直しの進め方:
- データを視覚化して現状把握
- 夫婦で一緒に分析結果を確認
- 削減可能な項目を洗い出し
- 優先順位をつけて改善計画を策定
- 実行後の効果測定
コミュニケーションのコツ:
- 責める雰囲気は一切作らない
- 「一緒に改善していこう」のスタンス
- データに基づいた客観的な議論
構造化思考を家計管理に応用
2つの構造化アプローチ
以前の記事「ITコンサルが教える!収益構造を見える化しないと失敗する理由」で紹介した構造化思考を、個人の家計管理にも応用しました。
1. 支出の構造化:
- 固定費 vs 変動費
- 必須費用 vs 選択的費用
- 投資 vs 消費 vs 浪費
2. 人生設計の構造化:
- 短期・中期・長期の目標設定
- ライフイベントに必要な資金計画
- リスク管理と機会創出のバランス
夫婦での価値観共有
実施したこと:
- 削れるところの意識合わせ
- 重視してお金をかけたいところの明確化
- 必要資金準備の優先順位決定
この構造化により、単なる節約ではなく、目的を持った家計管理が実現できました。
削減効果を投資に活用
削減分の有効活用
年間20万円以上の削減効果を、そのまま貯蓄に回すのではなく、将来への投資に活用しています。
活用方法:
- NISAでの積立投資
- 確定拠出年金の拠出額増加
- 緊急資金の充実
- 子どもの教育費準備
家計改善の好循環
固定費削減 → 投資資金確保 → 資産形成 → 家計の安定性向上 → さらなる最適化へのモチベーション向上
この好循環により、家計管理への取り組み意欲も維持できています。
継続するためのコツと注意点
無理をしない改善ペース
重要なのは一度にすべてを変えようとしないことです。私たちも段階的に改善を進めました。
継続のコツ:
- 大きな変化のタイミングに合わせて見直し
- 夫婦の価値観を尊重した改善
- 効果を数字で確認してモチベーション維持
- 完璧を求めすぎない
- 理屈と感情は分けて考える
- 目的と手段が一致している支出か確認
夫婦での協力が成功の鍵
価値観の違いへの対応:
- 妻の投資への心理的ハードルを段階的に解消
- お互いの「大切にしたいもの」は削減対象外
- データに基づいた客観的な議論
元々価値観が近かったこともあり、一度も揉めることなく改善を続けられています。
★総合評価
| 評価項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 削減効果 | ★★★★★ | 年間23万円削減、予想を上回る成果 |
| 実行しやすさ | ★★★★☆ | 段階的に進めれば無理なく実行可能 |
| 夫婦の満足度 | ★★★★★ | 価値観を尊重しながら改善、関係性も良好 |
| 継続しやすさ | ★★★★☆ | 定期的な見直しで無理のない継続が可能 |
| 家計の安定性 | ★★★★★ | 固定費削減により家計の安定性が大幅向上 |
| 投資への影響 | ★★★★★ | 削減分を投資に回すことで資産形成も加速 |
総合評価:★★★★★(4.7/5.0)
まとめ
この取り組みの最大の価値
家計の見直しは単なる節約ではありません。夫婦で将来を見据えた人生設計を共有し、目的を持ってお金を使う仕組み作りです。年間20万円以上の削減は手段であり、目的は家族の将来への投資と安心できる家計基盤の構築でした。
個人的な体験総括
最も印象的だったのは、支出の透明化による無駄遣いの自然減です。「見られている」という意識が働くだけで、購入前に「本当に必要?」と考える習慣がつきました。また、夫婦で価値観を共有することで、お金に関する不安やストレスが大幅に軽減されました。
特に結婚や出産などのライフイベントを控えた方、既に家庭を持っているが家計管理に不安を感じている方におすすめです。重要なのは、パートナーと一緒に取り組むこと。一人だけの努力では限界があります。
削減できた固定費は、ぜひ将来への投資に活用してください。私たちの場合、削減分をNISAや確定拠出年金に回すことで、節約と資産形成の両方を実現できています。
一緒に家計をカイゼンしていきましょう!
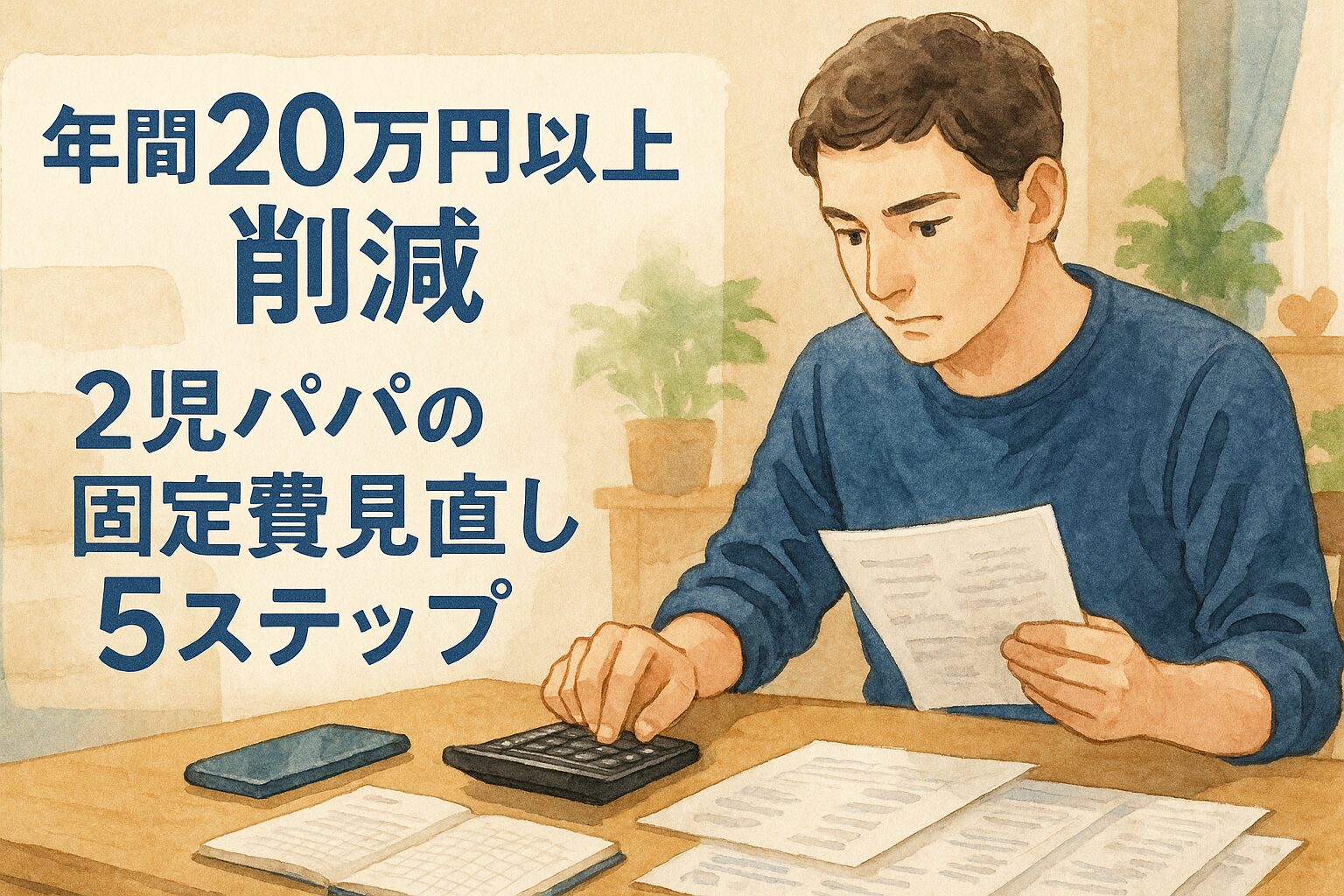


コメント