「カスタマージャーニーマップ?作ったけど全然使えない…」
多くの企業でこんな声を聞きます。せっかく時間をかけて作成したのに、実際のマーケティング施策に活かせずに終わってしまう。実はこれ、カスタマージャーニーマップ作成でよくある典型的な失敗パターンなんです。
CXコンサルとして様々な業界を見てきた中で、成功する企業と失敗する企業には明確な違いがあることが分かりました。その違いを理解すれば、初心者でも実務で使えるカスタマージャーニーマップを作ることができます。
本記事では、前回のCXコンサル紹介記事に続き、CXの具体的手法として「カスタマージャーニー設計の成功法則」を解説していきます。
こんな人におすすめ
✅ この記事がおすすめな人
- カスタマージャーニーマップを作ったが活用できていない
- 初めてカスタマージャーニー設計に挑戦したい
- マーケティング施策の効果を高めたい
- CXコンサルの思考法を学びたい
- 顧客理解を深めて売上向上を目指したい
そもそもカスタマージャーニーマップとは?
CX理論における位置づけ
カスタマージャーニーマップとは、CX(Customer Experience:顧客体験)を向上させるための中核的なフレームワークです。顧客が商品やサービスを知ってから購入し、その後も使い続ける一連の体験を時系列で可視化したものを指します。
定義と基本概念
CXコンサルの視点から解説すると、カスタマージャーニーマップは以下の5つの要素で構成されます:
| 要素 | 説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| ペルソナ(顧客像) | 具体的な顧客の人物像 | 30代子育て中の会社員女性 |
| フェーズ(段階) | 顧客体験の時間軸 | 認知→検討→購入→利用→推奨 |
| タッチポイント(接点) | 顧客との具体的な接触場面 | Web広告、店舗、アプリ、カスタマーサポート |
| 行動 | 各段階での顧客の具体的行動 | 検索、比較、問い合わせ、購入 |
| 感情・思考 | その時の顧客の心理状態 | 不安、期待、満足、不満 |
身近な例での解説
💡 初心者向け補足:美容院選びで考えてみましょう
認知段階:「髪を切りたい」→ネットで検索、友人の紹介
- 感情:「良い美容院ないかな?」(期待と不安)
検討段階:口コミ確認、料金比較、立地チェック
- 感情:「ここなら大丈夫そう」(安心感の向上)
購入段階:電話予約、来店、カウンセリング、施術
- 感情:「思った通りの仕上がり」(満足・不満)
利用段階:日常での使用感、周囲の反応
- 感情:「また行きたい」「やっぱり微妙だった」
推奨段階:友人への紹介、SNS投稿、リピート予約
- 感情:「みんなにも教えたい」(愛着・信頼)
これが基本的なカスタマージャーニーの流れです。
なぜカスタマージャーニーマップを作るのか?
ビジネス戦略上の重要性
CXコンサルとして業界を見てきた経験から言えば、カスタマージャーニーマップは単なる「顧客理解のツール」ではありません。戦略的なビジネス成果を生み出すための設計図なのです。
作成する目的とメリット
1. 顧客視点での課題発見
- 企業側の都合ではなく、顧客の立場で問題点を特定
- 見落としがちな「感情的な障壁」を可視化
2. マーケティング施策の精度向上
- どのタイミングで、どんなメッセージを、どのチャネルで届けるべきかが明確になる
- 無駄な広告費を削減し、ROI(投資対効果)を最大化
3. 部署間の認識統一
- マーケティング、営業、カスタマーサポートが同じ顧客像を共有
- 一貫した顧客体験の提供が可能
4. データドリブンな改善活動
- 各段階でのKPI(重要業績評価指標)設定が可能
- 定量的な効果測定と継続的な改善実行
作らないことのリスク
業界のベストプラクティスとして、カスタマージャーニーマップを作成していない企業には以下のリスクがあります:
- 顧客離脱ポイントの見落とし:なぜお客様が去っていくのか分からない
- マーケティング予算の無駄遣い:効果の薄い施策に投資し続ける
- 競合他社への顧客流出:より良い体験を提供する企業に負ける
- 従業員のモチベーション低下:なぜその業務が重要なのか理解できない
【CXコンサル視点】よくある5つの失敗例
業界での典型的な課題として、以下の失敗パターンが頻繁に見られます。
失敗例1:作成することが目的になってしまう
よくある状況 「上司に言われたからとりあえず作りました」「綺麗なマップが完成して満足」
なぜこの失敗が起こるのか
- 作成の目的が曖昧
- 完成後の活用方法を事前に決めていない
- 成果測定の仕組みがない
ビジネスインパクト
- 作成工数の無駄(通常20-40時間の投資が無駄に)
- 現場での活用が進まず、継続的な改善が止まる
失敗例2:理想的すぎるペルソナ設定
よくある状況 「当社の商品を絶対に買ってくれる完璧な顧客」を想定してマップを作成
なぜこの失敗が起こるのか
- 実際の顧客データではなく、希望的観測でペルソナを設定
- ネガティブな感情や行動を無視する傾向
- 1つのペルソナで全顧客を代表させようとする
ビジネスインパクト
- 実際の顧客行動とのギャップが大きく、施策が的外れになる
- 顧客の不満や離脱要因を見落とす
失敗例3:企業視点での作成
よくある状況 「お客様はきっとこう思っているはず」という企業側の推測でマップを作成
なぜこの失敗が起こるのか
- 顧客インタビューやアンケートを実施していない
- 営業やサポート部門の現場の声を聞いていない
- データ分析を行わずに作成している
ビジネスインパクト
- 顧客の真のニーズを捉えられない
- 改善施策が顧客満足度向上に繋がらない
失敗例4:作りっぱなしで更新しない
よくある状況 「1年前に作ったマップをそのまま使い続けている」
なぜこの失敗が起こるのか
- 定期的な見直しプロセスがない
- 市場変化や顧客行動の変化を反映していない
- 担当者の異動で引き継がれていない
ビジネスインパクト
- 時代遅れの顧客理解に基づいた施策実行
- 新しいタッチポイント(SNS等)の見落とし
失敗例5:詳細すぎて実用性がない
よくある状況 「A3サイズ10ページの超詳細マップを作成したが、誰も見ない」
なぜこの失敗が起こるのか
- 完璧主義による過度な詳細化
- 利用者(現場スタッフ)の使いやすさを考慮していない
- 重要度に応じた情報の取捨選択ができていない
ビジネスインパクト
- 現場での活用率が低下
- 意思決定スピードの低下
💡 初心者向け補足 これらの失敗例は、多くの企業で実際に起こっている問題です。最初から完璧を目指さず、「まずは使える70点のマップを作る」ことから始めましょう。
【実務で使える】成功するための5つのコツ
理論的根拠を踏まえて、失敗例を回避する具体的な成功法則をご紹介します。
コツ1:明確な目的設定と成果指標の定義
理論的根拠 目的が曖昧なプロジェクトは、ゴールが見えないため継続的な改善活動に繋がりません。
実装時の注意点
- 「なぜ」「何のために」作るのかを一言で表現できるまで明確化
- 定量的な成果指標(KPI)を事前に設定
- 3ヶ月後、6ヶ月後の具体的な成果目標を明記
成果測定の考え方
例:ECサイトのカート離脱改善が目的の場合
・KPI:カート離脱率を30%→20%に改善
・期限:3ヶ月以内
・測定方法:Google Analyticsでの月次モニタリング
コツ2:データに基づくペルソナ設計
理論的根拠 データドリブンなアプローチにより、企業の思い込みを排除し、実際の顧客行動に基づいた設計が可能になります。
実装時の注意点
- 既存顧客アンケート、インタビューの実施(最低30-50名、できれば100名以上)
- Web解析データ、購買データの分析
- 営業・サポート担当者へのヒアリング
品質確保のチェックポイント
- 実在の顧客データに基づいているか
- ネガティブな感情・行動も含まれているか
- 複数のペルソナパターンを検討したか
コツ3:シンプルで実用的な構成
理論的根拠 複雑すぎるマップは現場での活用率が著しく低下し、意思決定の迅速性を損ないます。
実装時の注意点
- A4用紙1-2枚に収まるサイズ
- 重要度の高い情報のみを厳選
- 現場スタッフが5分で理解できるレベル
実用的な構成例
横軸:認知→検討→購入→利用→推奨(5段階)
縦軸:
・顧客の行動(何をするか)
・感情・思考(どう感じるか)
・タッチポイント(どこで接触するか)
・改善機会(何を改善できるか)
コツ4:継続的な更新とPDCAサイクル
理論的根拠 顧客行動と市場環境は常に変化するため、静的なマップでは実際の状況とのギャップが拡大します。
実装時の注意点
- 3ヶ月や半年に1回の定期見直し
- 新しいデータや顧客の声を反映
- 改善施策の効果測定結果をマップに反映
継続改善のプロセス
- 現状のマップで施策実行
- 結果の測定・分析
- 新たな課題・機会の発見
- マップの更新・改善
- 次の施策実行(PDCAサイクル)
コツ5:組織全体での共有と活用
理論的根拠 カスタマージャーニーマップの価値は、組織全体で顧客理解を統一し、一貫した顧客体験を提供することにあります。
実装時の注意点
- マーケティング、営業、サポート部門での共有会実施
- 各部門での具体的な活用方法を明確化
- 定期的な振り返り会議でマップの活用状況を確認
部門別活用例
- マーケティング:広告メッセージとタイミングの最適化
- 営業:提案内容と顧客の関心事項のマッチング
- サポート:問い合わせ内容の予測と対応品質向上
- 商品開発:顧客ニーズに基づく機能改善
業界別活用パターン分析
CXコンサルとしての業界知識を活かし、主要な業界での活用パターンをご紹介します。
BtoB SaaS業界の特徴
業界特有の課題
- 長い検討期間(3-12ヶ月)
- 複数の関係者による意思決定
- トライアル期間での離脱率の高さ
カスタマージャーニー設計のポイント
認知段階:課題認識→情報収集(3-6ヶ月)
・タッチポイント:業界メディア、ウェビナー、ホワイトペーパー
・重要な感情:「本当に解決できるのか?」(不安)
検討段階:比較検討→社内稟議(1-3ヶ月)
・タッチポイント:デモ、資料請求、営業面談
・重要な感情:「他社との違いは?」「費用対効果は?」
導入段階:契約→初期設定→運用開始(1-2ヶ月)
・タッチポイント:オンボーディング、サポート、研修
・重要な感情:「使いこなせるか不安」→「効果を実感」
ECサイト運営での応用
デジタルマーケティング視点での特徴
- 短時間での意思決定
- 比較検討行動の可視化
- リピート購入の重要性
設計上の重要ポイント
認知段階:SNS、検索、広告(数分-数日)
・感情の変化:「面白そう」→「欲しいかも」→「買おうかな」
・離脱要因:価格、送料、口コミ不足
購入段階:カート投入→決済(数分-数時間)
・最大の課題:カート離脱率(平均70%)
・改善ポイント:入力フォーム、決済方法、送料表示
購入後:配送→受取→使用→評価(1-4週間)
・リピート要因:商品満足度、配送体験、アフターサービス
サービス業での展開方法
CX設計論から見た特徴
- 人的サービスの品質が重要
- 感情的な満足度の影響が大きい
- 口コミ・紹介の影響力が強い
成功パターンの共通要素
- 予約段階:手軽さ、分かりやすさ
- 来店段階:待ち時間、雰囲気、スタッフ対応
- サービス提供中:技術力、コミュニケーション
- 帰宅後:満足感の持続、次回予約の動機
💡 初心者向け補足 業界によって顧客の行動パターンは大きく異なります。自社の業界特性を理解した上で、他業界の成功事例も参考にすることで、より効果的なマップが作成できます。
【ステップバイステップ】作成手順
フレームワークの選定理由を含めて、実務レベルでの具体的な作成手順をご説明します。
ステップ1:目的と成果指標の明確化(30分)
フレームワークの理論的背景 目的設定にはSMARTフレームワーク(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)を活用します。
具体的な作業内容
- プロジェクトゴールの設定
- 成果指標(KPI)の定義
- 期限と責任者の明確化
チェックポイント
- 一言で説明できる明確な目的があるか
- 定量的な成果指標が設定されているか
- 3-6ヶ月以内の実現可能な目標か
ステップ2:ペルソナの設定(1-2時間)
データ収集の方法
- 既存顧客アンケート(30-50名以上)
- 営業・サポート担当者へのインタビュー
- Web解析データの分析
- 競合他社の顧客層調査
ペルソナ設定シート
【基本情報】
・年齢、性別、職業、年収
・居住地、家族構成
【行動特性】
・情報収集方法、購買パターン
・よく利用するサービス・メディア
【課題・ニーズ】
・抱えている問題、解決したいこと
・重視する価値観、優先順位
【感情特性】
・性格、価値観
・商品・サービスに対する期待と不安
ステップ3:カスタマージャーニーフェーズの定義(30分)
業界標準のフェーズ構成
BtoC向け:認知→興味→検討→購入→利用→推奨
BtoB向け:課題認識→情報収集→比較検討→稟議→導入→活用→拡大
自社に適したフェーズのカスタマイズ
- 業界特性を反映
- 実際の顧客行動データに基づく調整
- 各フェーズの期間も設定
ステップ4:各フェーズの詳細マッピング(2-3時間)
マッピング項目 各フェーズで以下の4要素を具体的に記載:
- 顧客の行動:何をするか(検索、比較、問い合わせ等)
- 感情・思考:どう感じるか(不安、期待、満足等)
- タッチポイント:どこで接触するか(Web、店舗、電話等)
- 痛み・機会:改善できるポイントは何か
記載のコツ
- 顧客の言葉で表現(「コスパが良い」「使いやすい」等)
- ポジティブとネガティブ両方の感情を含める
- 具体的な行動を動詞で表現
ステップ5:改善ポイントの特定(1時間)
優先度付けの方法 改善ポイントを以下の2軸で評価:
- インパクト:改善した場合の効果の大きさ(高・中・低)
- 実現容易性:実装の難易度(易・中・難)
改善案の具体化
- 短期(1-3ヶ月)で実現可能な施策
- 中長期(6-12ヶ月)の抜本的改善
- 必要なリソース(人・予算・時間)の見積もり
ステップ6:完成度チェックと調整(30分)
品質確保のチェックリスト
- 実際の顧客データに基づいているか
- 各部門の担当者が理解・活用できる内容か
- 改善ポイントが具体的に明示されているか
- 定期更新のプロセスが決まっているか
💡 初心者向け補足 最初は完璧を目指さず、70点レベルで一度作成し、実際に使いながら改善していくことが重要です。1週間以内に初版を完成させることを目標にしましょう。
【応用編】家庭生活での活用
CX思考の汎用性を活かし、日常生活への落とし込み方法をご紹介します。
子供の習い事選びジャーニー
CX設計論の応用 子供の習い事選びも、実は立派なカスタマージャーニーです。
認知段階:「習い事させたいな」
・きっかけ:周りの子の話、子供の興味
・感情:「何がいいかな?」(期待と迷い)
情報収集段階:ネット検索、口コミ確認
・行動:体験レッスン検索、料金比較
・感情:「通えるかな?」「続けられるかな?」(不安)
体験段階:見学、体験レッスン参加
・重要ポイント:子供の反応、先生の対応、雰囲気
・感情:「ここなら安心」or「微妙かも」
入会段階:申し込み、初回レッスン
・離脱要因:手続きの煩雑さ、初回の印象
・感情:「良い選択だった」(安心と期待)
継続段階:定期レッスン、成果確認
・満足要因:子供の成長実感、コミュニティ形成
・感情:「通わせて良かった」(満足と誇り)
家族の外食選びプロセス
日常生活への実践的応用
家族会議段階:「今日どこで食べる?」
- 各自の希望の確認
- 予算と時間の制約整理
- 妥協点の模索
候補選定段階:「あそこはどうかな?」
- 過去の経験、口コミ確認
- アクセス、混雑状況のチェック
- 子供連れでも大丈夫かの判断
決定・移動段階:「じゃあ行こうか」
- 最終的な意思決定
- 移動時間と手段の選択
- 待ち時間の覚悟
食事体験段階:実際の外食
- 料理の味、サービス品質
- 子供の機嫌、家族の会話
- コストパフォーマンスの実感
事後評価段階:「今日は良かったね」
- 家族での振り返り
- 次回利用の意向確認
- 他の人への推奨意思
家事効率化のジャーニーマップ
CX思考による生活改善
私自身も家庭で実践している方法ですが、家事を「家族の体験」として捉え直すことで、大幅な効率化を実現できました。
朝の準備ジャーニー
起床→朝食準備→子供の身支度→出発
各段階での課題:
・起床:なかなか起きない(子供)
・朝食:準備時間がかかる
・身支度:持ち物忘れが多い
・出発:時間に間に合わない
改善施策:
・前日夜の準備の仕組み化
・朝食メニューのパターン化
・持ち物チェックリストの見える化
・余裕を持ったタイムスケジュール
この考え方により、朝の準備時間を30分短縮し、家族のストレスも大幅に軽減できました。
💡 初心者向け補足 家庭でカスタマージャーニー思考を使うコツは、「家族一人ひとりの立場で考える」ことです。子供、配偶者、自分、それぞれの視点で体験を見直すと、意外な改善ポイントが見つかります。
よくある質問と回答
Q1: カスタマージャーニーマップ作成にどのくらい時間がかかりますか?
A1: 初回作成の場合、以下が目安です:
- 簡易版:1日(8時間)
- 標準版:3-5日(24-40時間)
- 詳細版:1-2週間(40-80時間)
初心者の方は、まず簡易版から始めて、使いながら詳細化していくことをお勧めします。
Q2: 一人でも作成できますか?
A2: 可能ですが、以下の点で複数人での作成を推奨します:
- 多角的な視点:異なる部署の知見を活用
- 客観性の確保:思い込みを排除
- 組織での活用促進:作成プロセスへの参加で当事者意識向上
最低でも営業・マーケティング・サポートから1名ずつの参加が理想的です。
Q3: どのツールを使えばいいですか?
A3: 目的と予算に応じて選択:
- 無料ツール:PowerPoint、Googleスライド、Miro
- 専用ツール:Lucidchart、Figma
- オンライン協業:Miro、Microsoft Whiteboard
初心者はPowerPointでの作成から始めることをお勧めします。
Q4: BtoBとBtoCで作り方は違いますか?
A4: 基本的な作成方法は同じですが、以下の違いがあります:
| 項目 | BtoB | BtoC |
|---|---|---|
| 検討期間 | 長い(3-12ヶ月) | 短い(数分-数日) |
| 意思決定者 | 複数人 | 個人または家族 |
| 重視要素 | ROI、機能性 | 感情、体験 |
| タッチポイント | 営業、展示会 | 広告、店舗 |
Q5: 更新頻度はどのくらいが適切ですか?
A5: 以下を目安に定期的な見直しを実施:
- 四半期見直し:数値データの更新、小さな改善
- 半年見直し:市場変化の反映、大きな修正
- 年次見直し:全面的な再検討、戦略変更の反映
ただし、大きな市場変化や新サービス導入時は随時更新が必要です。
★総合評価:カスタマージャーニー設計の価値
カスタマージャーニーマップ作成の投資対効果
| 評価項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 顧客理解度向上 | ★★★★★ | 定量・定性両面での深い顧客理解が可能 |
| マーケティング効率 | ★★★★★ | 無駄な施策を削減し、ROI向上に直結 |
| 組織内連携 | ★★★★☆ | 部署間の顧客理解統一に大きく貢献 |
| 作成コスト | ★★★☆☆ | 初期投資は必要だが、中長期でペイ |
| 継続性 | ★★★★☆ | 定期更新の仕組み化で価値を維持 |
| 実用性 | ★★★★★ | 日々の意思決定に直接活用可能 |
総合評価:★★★★☆(4.3/5.0)
成功のための重要ポイント
カスタマージャーニー設計の成功は、以下3つの要素にかかっています:
- データに基づく客観的な設計
- 継続的な更新と改善
- 組織全体での活用
これらを徹底することで、単なる「作って終わり」ではなく、実際のビジネス成果に繋がるツールとして活用できます。
まとめ
カスタマージャーニーマップは、顧客体験向上とビジネス成果創出のための強力なツールです。しかし、作成すること自体が目的ではありません。実際の顧客理解を深め、具体的な改善活動に繋げることが本来の価値です。
この記事の3つのポイント
- 失敗例を知ることで、効果的なマップ作成が可能
- 作成目的の明確化、データに基づくペルソナ設定、継続的な更新が成功の鍵
- 業界特性を踏まえた設計で実用性が向上
- BtoB、BtoC、業界ごとの特徴を理解した上での設計が重要
- 家庭生活にも応用できるCX思考
- ビジネスで学んだ顧客視点は、家族の満足度向上にも活用可能
CXコンサルとして大切にしていること
- 顧客の立場に立った本質的な課題発見
- データに基づく客観的な分析と改善提案
- 継続的なPDCAサイクルによる価値向上
カスタマージャーニーマップは、お客様に「また利用したい」と思ってもらえる体験設計の出発点です。完璧を求めず、まずは70点のマップから始めて、使いながら改善していくことが成功への近道です。
一緒により良い顧客体験を設計していきましょう!
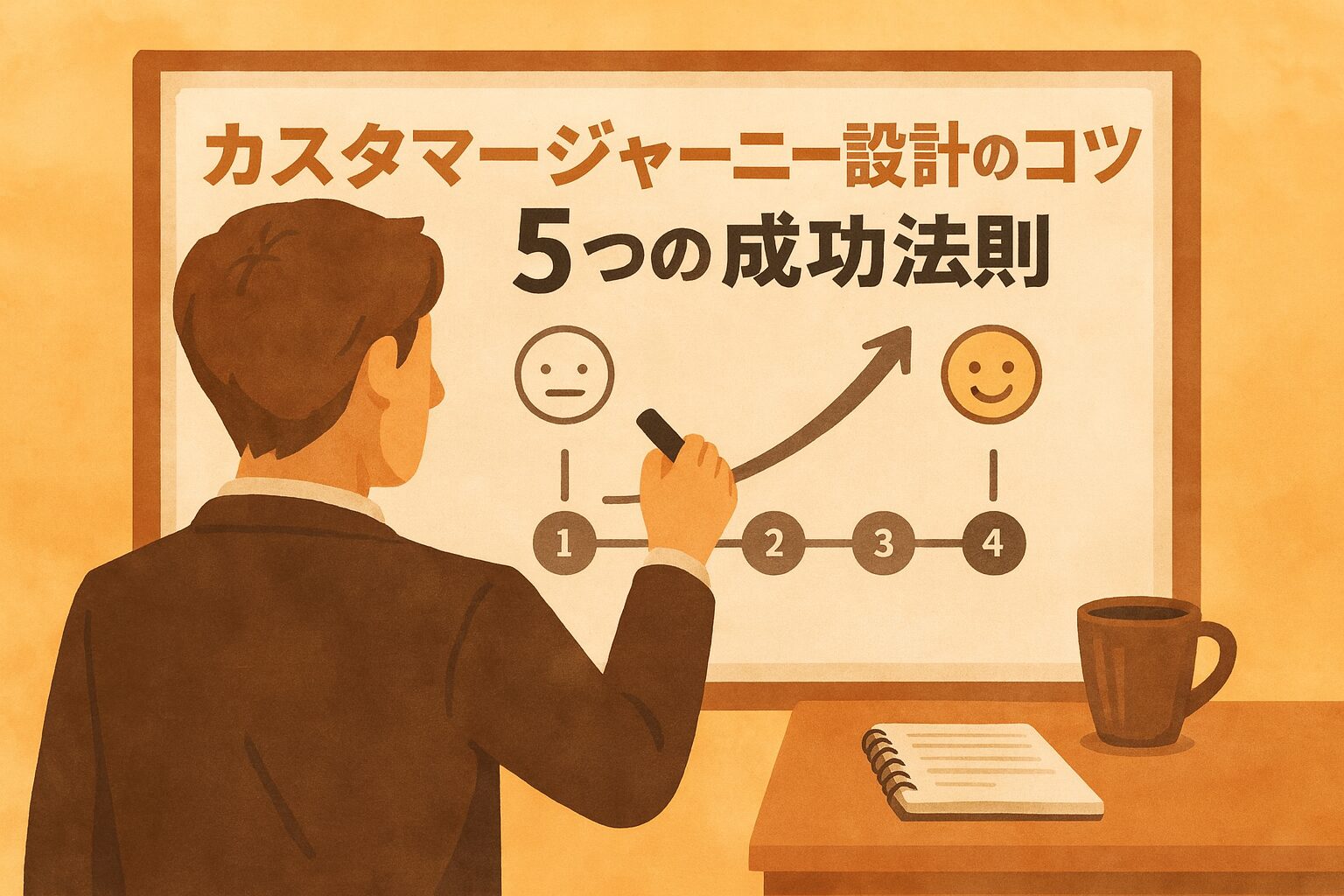


コメント