「今の会社で定年まで働ける自信、ありますか?」
社会人6年目、私は3社目への転職活動をしていました。しかし実は、本気で転職するつもりはありませんでした。ただ「自分の市場価値を確認したい」「世の中で求められているスキルを知りたい」という思いから、転職エージェントと定期的に面談を続けていたのです。
現在、ITコンサルとして5社を経験してきた私は、転職後も継続的に転職エージェントと面談を続けています。転職する予定がなくても、半年に1回は市場動向や自分の市場価値をチェック。この習慣が、予期せぬキャリアの危機から身を守る「キャリア自衛策」になっています。
転職シリーズとして、今回は大手リストラ時代を生き抜くための、実践的なキャリア形成術をお届けします。
こんな人におすすめ
✅ この記事がおすすめな人
- 今の会社に不満はないが将来が不安な人
- 自分の市場価値を把握したい人
- 転職活動の時間が取れない忙しい社会人
- 突然のリストラに備えたい人
- 家族がいて転職リスクを最小化したい人
なぜ今「転職活動をしないリスク」が問題なのか
変わりゆく雇用の常識
「大手企業に入れば安心」「終身雇用で定年まで安泰」──そんな神話は、もはや過去のものになりつつあります。
2025年、日本の上場企業で人員削減が加速しています。早期退職の募集人数は8ヶ月で1万人を突破し、2024年通年を早くも上回りました。しかも約6割が黒字企業による「黒字リストラ」です。
パナソニック、三菱電機、富士通──誰もが知る大手企業でさえ、業績が黒字にもかかわらず、競争力強化や事業再編を目的に大規模な人員削減を実施しています。
私が転職活動を続ける理由
私がなぜ転職後も継続的に転職活動(市場価値のチェック)を続けているのか。
それは、突然のリストラや会社の倒産に備えるためだけではありません。
本当の理由は3つあります:
- 自分の市場価値を正確に把握するため
社内評価と市場評価は必ずしも一致しません。定期的にチェックすることで、自分の強みと弱みを客観的に理解できます。 - 世の中で求められているスキルを知るため
AIやクラウドなど、流行りのスキルは常に変化します。今の会社で習得できるスキルが、将来も価値があるのかを見極める必要があります。 - ポータブルスキルを意識的に磨くため
社内でしか通用しないスキルばかり身につけていないか、常にチェックする習慣が大切です。
データで見る雇用環境の激変
2025年の衝撃データ
早期退職募集の実態
- 募集人数:8ヶ月で1万人超(2024年通年を突破)
- 黒字リストラ:約6割が黒字企業
- ターゲット:45歳以上の管理職年代が中心
- 業界:製造業を中心に大規模削減
主なリストラ(早期退職募集)企業
- パナソニックHD:国内10,000人規模の募集
- 三菱電機:満53歳以上を対象、人数上限なし
- リクルートHD:約4,000人の人員削減
転職市場のトレンド
2024年の転職率
- 正社員の転職率:7.2%(高水準を維持)
- 40-50代で増加傾向:若手は減少、ベテラン層が増加
- 転職後の平均年収:509.3万円(転職前より22.0万円増)
企業の採用姿勢
- 転職求人倍率:2.42倍(前月差±0.00ポイント)
- 中途採用積極化:1社平均20.8人を採用
- 年収アップ傾向:転職で年収が上がった人は約35%
売り手市場の継続
2024年春季労使交渉の賃上げ率は大手企業で平均5.33%(前年3.60%)に達し、約30年ぶりの高い伸びとなりました。特にIT・コンサル業界では人材獲得競争が激化しています。
終身雇用の現実
終身雇用神話の崩壊
- 終身雇用支持率:82.0%(ピーク時から減少)
- 若い世代:転職志向が増加
- 生え抜き社員:割合は減少傾向
💡 初心者向け補足
転職市場は「売り手市場」が続いていますが、大手企業でもリストラが進んでいます。つまり、「転職したい人にはチャンスがある」一方で、「準備していない人は突然のリストラに対応できない」という二極化が進んでいるのです。
転職活動をしない5つのリスク
リスク1:社内スキルへの過度な依存
社内スキルの罠
1つの会社に長く勤めていると、気づかないうちに「その会社でしか通用しないスキル」ばかりが身についてしまいます。
私の実体験:
2社目では、グループ会社との関係性や、ニッチな業界・業務への特定領域の専門知識に依存していました。転職活動を通じて、それらが「社外では評価されにくいスキル」だと気づいたのです。
よくある社内スキル:
- グループ会社や関連企業との人脈・関係性
- 社内特有のシステムやプロセスの知識
- 特定業界・特定顧客に限定された専門知識
- 社内政治をうまく立ち回る能力
リスク2:市場価値の把握不足
自分の年収は適正か?
社内評価と市場評価は大きく異なることがあります。私自身、高い年収をもらっていたので「これ以上は難しいだろう」と思っていましたが、実際には想定以上の年収アップ提示をしてくれる企業が複数ありました。
転職を重ねることで得たCX専門コンサルから多領域経験後の変化
- CXのみの経験時:求人の幅が限定的
- CX+他領域の経験後:求人の幅が劇的に拡大
- CX以外も理解していることで、部署横断・コラボレーションを進めたい企業からの打診
市場価値を把握しないリスク:
- 本来もらえるはずの年収を逃す
- スキルの方向性を間違える
- キャリアの選択肢が狭まる
リスク3:給与水準の認識ギャップ
年収レンジの実態
私は前職で1000万円台半ばの年収をいただいていました。
正直、「この年収レンジでも、さらに上がる可能性があるんだ」と知ったときは驚きました。
転職活動を通じて分かったことは、自分が思っている以上に市場は自分を評価してくれる可能性があるということです。
定期的なチェックの重要性:
- 年収が適正か分からないまま働き続けるリスク
- 社内評価と市場評価のズレを放置するリスク
- 転職のベストタイミングを逃すリスク
リスク4:ポータブルスキル習得の機会損失
世の中で求められているスキルが分からない
転職エージェントとの定期面談で得られる情報の中で、最も価値があるのが「世の中で求められているスキル」の情報です。
常に需要があるスキル:
- プロジェクトマネジメント
- データ分析
- 問題解決能力、論点整理力
- プレゼンテーション能力
流行りのスキル(2025年現在):
- 生成AI活用スキル
- AIマーケティング
- クラウド技術
- データサイエンス
今の会社で習得可能なスキルの見極め
現職で学べるスキルが市場価値に繋がるかを確認することで、スキル習得の方向性を間違えずに済みます。
リスク5:突然のリストラに対応できない
準備なしでの転職活動は不利
突然リストラされてから転職活動を始めると、以下のような問題が発生します:
- 職務経歴書が古いまま:直近の実績が整理されていない
- ネットワークが限定的:社内の人脈しかない
- 焦りから判断ミス:冷静な転職先選びができない
- 交渉力の低下:「早く決めたい」焦りで年収交渉で不利に
私が実践していること:
- 半年に1回、職務経歴書を更新
- LinkedInプロフィールの定期整備
- 転職エージェントとの継続的な関係維持
社内スキル vs ポータブルスキル
社内スキルの例
転職時に評価されにくいスキル:
- グループ会社との関係性や人脈
- 社内特有のシステム・プロセス知識
- 特定業界・特定顧客に限定された知識
- 社内政治の立ち回り方
💡 初心者向け補足
社内スキルが「悪い」わけではありません。ただし、社内スキルばかりに依存すると、転職市場での選択肢が狭まるリスクがあります。
ポータブルスキルの例
どの会社でも通用するスキル:
私が転職時に評価されたスキル:
- プロジェクトマネジメント
規模や業界を問わず、プロジェクトを成功に導く能力 - データ分析
データに基づく意思決定支援の能力 - コンサルティング能力
論点整理、問題解決能力、課題整理能力、プレゼンテーション能力、提案検討力、資料作成能力 - ITスキル
プログラマーやSE経験から培った技術的知識 - 特定領域の専門知識
CXコンサルティングの経験と実績
実体験:CX専門→多領域経験の効果
私のキャリア戦略:
- 1社目→2社目:プログラマー/SE→コンサル転身
- 2社目→3社目:CX内での経験領域拡大
- 3社目→4社目:CX以外の領域への挑戦(セキュリティなど)
- 4社目→5社目:CX回帰+AI活用の深化
戦略的なキャリア形成の結果:
- 「CXしかできない人」→「CX+多領域対応可能な人」へ
- LinkedInや転職エージェントからのオファーの質が変化
- 部署横断・コラボレーション案件の打診増加
- 「自分はやはりCXが好き」という適性の再確認
💡 CX(Customer Experience)とは?
顧客体験を設計・改善する専門領域です。詳しくはCXコンサルって何してる人?の記事で解説しています。
転職活動から得られる3つの情報
転職する予定がなくても、転職活動(エージェントとの面談)から得られる情報は非常に価値があります。
情報1:自分の市場価値(年収レンジ)
エージェントとの面談で分かること:
- 自分の経験・スキルが市場でどう評価されるか
- 想定年収レンジの具体的な数字
- 社内評価と市場評価のギャップ
私の実例:
私は前職で1000万円台半ばの年収をいただいており、「年収は現状維持が精一杯だろう」と考えていました。
しかし、想定以上の年収アップ提示が複数の企業からありました。
高い年収をいただいていても、市場にはさらに高く評価してくれる企業が存在する可能性があります。それを知ることで、キャリアの選択肢が広がります。
情報2:世の中で求められているスキル
エージェントから得られる情報:
- 転職者の情報
どんな人がどんな求人を求めて転職しているのか - 企業ニーズの情報
どんな企業がどんなスキルを持った人を探しているのか - 転職動向の情報
世の中の転職動向(売り手市場 or 買い手市場)
具体例(2025年現在):
- AI活用スキル:圧倒的に需要が高い
- データ分析:あらゆる業界で求められる
- プロジェクトマネジメント:常に需要が高い
- セキュリティ:IT人材不足で需要急増
情報3:今の会社で習得可能なスキルの見極め
最も重要な気づき:
転職市場で求められているスキルを知ることで、「今の会社で学べるスキルが、将来も価値があるのか」を判断できます。
私の実践:
現職(5社目)では、AI活用に特に力を入れている企業を選びました。理由は、エージェントとの面談で「AI活用スキルの需要が爆発的に高まっている」と知ったからです。
現職で意識的に磨いているスキル:
- AI活用案件の積極的な参加
- AIに関する知識の習得
- 部署立ち上げに関するスキル・経験
💡 初心者向け補足
「今の会社でスキルを磨く」ことと「転職活動で市場を知る」ことは矛盾しません。むしろ、市場を知ることで、今の会社で何を学ぶべきかが明確になります。
転職エージェントの「転職しない」活用法
JACリクルートメントとの継続的な関係
私の活用パターン:
- 転職直後の半年間:3ヶ月に1回面談
- その後:半年に1回のペースで情報交換
- 担当者との関係:コンサル業界担当者との信頼関係構築
なぜ転職後も面談を続けるのか:
転職エージェントにとって、私は「将来的な転職候補者」であり、「人材紹介先としての企業担当者」でもあります。つまり、Win-Winの関係が成り立つのです。
面談で得られる情報
定期面談で話す内容:
- 転職者の情報
どんな人がどんな求人を求めて転職しているか - 企業ニーズの情報
どんな企業がどんなスキルを探しているか - 転職動向の情報
売り手市場なのか、買い手市場なのか - 自分の市場価値の確認
今転職するなら、どんな選択肢があるか
JACリクルートメントの特徴
他社エージェントとの違い:
一般的なエージェント(リクルート、マイナビなど):
- 求職者に担当者が付く
- 担当者が求人を見つけて紹介
- 各企業の担当者から情報をヒアリング
JACリクルートメント:
- 求職者に担当が付かない
- 各企業担当者(複数企業担当)が直接紹介
- 企業側の本音が聞きやすい仕組み
私のケース(特殊例):
3社目→4社目の転職時に紹介してくれたコンサル業界担当の方が、その後昇格され、コンサル企業担当を取りまとめるポジションになりました。その方と継続的に関係を維持しています。
人材紹介の相談
双方向の情報交換:
個人としての面談とは別に、会社として「こんな人を探している」という採用相談も実施しています。人事も含めた打ち合わせで、転職者を紹介してもらうための情報共有を行います。
これのメリット:
- 他部署含めた自社の採用ニーズをリアルに知れる
- 自社で求められる人材像を客観視できる
- エージェントとの関係がより強固になる
💡 初心者向け補足
「転職する気がないのに面談するのは申し訳ない」と思う必要はありません。エージェントにとって、あなたは「将来的な転職候補者」として、カスタマージャーニーの「検討段階」にあたります。つまり、エージェント側も「リード育成期間」として捉えているので、気にせず活用しましょう。
おすすめ転職エージェント3選+α
私が実際に利用して良かったエージェントをご紹介します。
1. JACリクルートメント
強み:
- 企業担当者が直接紹介するスタイル
- ハイクラス求人に強い(年収800万円以上)
- 企業側の本音が聞きやすい
向いている人:
- 年収800万円以上を目指す人
- 専門性が高い職種の人
- 企業の内情をしっかり知りたい人
私の活用法:
- 半年に1回の定期面談
- 市場動向の情報収集
- 自分の市場価値の確認
2. リクルートエージェント / マイナビエージェント/doda
強み:
- 求職者に担当が付く丁寧なサポート
- 幅広い業界・職種の求人
- 初めての転職でも安心
向いている人:
- 初めて転職する人
- 幅広い選択肢から選びたい人
- じっくり相談しながら進めたい人
私の活用法:
- 初期の転職(1社目→2社目、2社目→3社目)で利用
- 4社目以降はJAC経由で転職していますが、登録はしており、企業への応募もしています
(結果、JAC経由で応募した企業のオファー内容(年収や仕事内容など)が一番良くて転職先を決めています。) - JACと併用して情報を多角的に収集
3. ビズリーチ
強み:
- 企業から直接スカウトが来る
- 市場価値が分かりやすい
- ハイクラス求人が豊富
注意点:
- 有料サービス(月額制)
- 無料会員だと機能制限あり
私の活用法:
- 1ヶ月無料キャンペーンを活用
- 本気で転職する時期のみ有料会員
- 無料期間外は無料会員として登録継続
併用戦略のすすめ
推奨の組み合わせ:
JAC + リクルート/マイナビ/doda + ビズリーチの3本柱
理由:
- JACだけでは情報が偏る可能性
- 求職者担当型(リクルート/マイナビ/doda)と企業担当型(JAC)の両方を活用
- ビズリーチで企業からの直接スカウトも確認
複数登録のメリット:
- 市場価値を多角的に把握できる
- 各エージェントの得意分野を活かせる
- 1つのエージェントに依存しない
💡 初心者向け補足
最初はすべて無料で使え、求職者に担当が付く、リクルートエージェントかマイナビエージェント、dodaから始めるのがおすすめです。
慣れてきたら求職者に担当が付かないJACや有料のビズリーチを追加しましょう。
実践:転職活動を習慣化する方法
新卒2年目から始めるべき理由
おすすめのタイミング:新卒2年目の半ば(入社1年半後)
理由:
- 最低限の職務経歴ができている
1年半の実務経験があれば、エージェントも具体的なアドバイスができます - 世の中で何を求められているか分かる
自分のスキルが市場でどう評価されるかを早期に知れます - 自分の年収が適正か判断できる
同年代の転職者の年収水準を知ることができます - キャリアの方向性を修正できる
早い段階で軌道修正できるのは大きな強みです
「転職する可能性低いし、申し訳ない」は不要
転職エージェントにとって、あなたは「将来的な転職候補者」です。カスタマージャーニーでいう「検討段階」にあたり、エージェントも「リード育成期間」として捉えています。
つまり、お互いにメリットがある関係なのです。
定期面談の実践方法
私の実践スケジュール:
- 最初の半年:3ヶ月に1回面談
転職直後はエージェントが転職後の状況を気になっていることが多いので、
情報共有に加えて、市場動向の変化を細かくチェック - その後:半年に1回のペース
定期的な市場価値確認と情報収集 - 職務経歴書の定期更新
半年に1回、直近の実績を追加 - LinkedInプロフィールの整備
年に1-2回、スキルや経験を更新
面談で聞くべきこと:
- 自分と同じような経験・スキルの人がどんな企業に転職しているか
- 今の市場で求められているスキルは何か
- 自分が転職するなら、どんな選択肢があるか
- 想定年収レンジはどのくらいか
転職すべきタイミング4つ
転職活動を続けていると、「本当に転職すべきタイミング」が見えてきます。
タイミング1:新たなスキル・経験を得たいとき
私の実例:
3社目→4社目の転職理由
CXしかやっていないことで「CX以外はできるのか?」と見られることを知り、CX以外の領域(セキュリティなど)も経験しようと決意。
結果として、CX以外の経験を積んだことで、求人の幅が劇的に拡大しました。
4社目→5社目の転職理由
CX以外の領域を経験した結果、「自分はやはりCXが好き」と再確認。加えて、転職エージェントやLinkedInから様々な企業・部署からお話が来るようになり、「CX領域以外も対応できる人」というキャリアは積めたと認識。
さらに、AI活用を進めているCXコンサル企業という理想の環境を見つけたため、転職を決意。
タイミング2:市場価値と年収が合っていないとき
判断基準:
- エージェント面談で複数の企業から年収アップ提示
- 社内評価と市場評価に大きなギャップ
- 同業他社の年収水準が明らかに高い
注意点:
年収だけで転職を決めるのはリスクがあります。スキルの習得可能性、ワークライフバランス、企業文化なども総合的に判断しましょう。
タイミング3:非ポータブルスキルばかり身につく環境
危険なサイン:
- 社内特有のシステム・プロセスの知識ばかり増える
- グループ会社との関係性に依存した仕事が多い
- 転職市場で評価されるスキルが習得できない
私の経験:
2社目では、特定領域の専門知識に依存していることに気づき、より汎用的なスキルを磨ける環境への転職を決意しました。
タイミング4:ライフステージの変化
私のケース:
結婚・子育てにより、ワークライフバランスの優先順位が変化しました。
現職(5社目)転職時の優先順位:
- リモートワーク中心(最優先)
- スキル・経験の習得可能性
- 得られる経験の幅
- 年収
結果:
現職では8割がリモートワーク。家族時間を確保しながら、AI活用という最先端のスキルも磨ける理想的な環境を実現できました。
💡 初心者向け補足
ライフステージによって、キャリアの優先順位は変わります。独身時代は「スキル・経験」優先、家族ができたら「ワークライフバランス」優先──そんな柔軟な判断が大切です。
家族がいる場合の転職判断軸
2児のパパ視点での優先順位
独身時代と家族ができた後では、優先順位が大きく変わります。
私の現職(5社目)転職時の優先順位:
- リモートワーク中心(最優先)
- スキル・経験の習得可能性
- 得られる経験の幅
- 年収
リモートワークが「スキルよりも経験よりも年収よりも大切」でした。理由は、子供との時間を最優先したかったからです。
ライフステージに合わせた柔軟な判断:
- 独身時代:スキル・経験・年収を優先
- 結婚直後:ワークライフバランスと年収のバランス
- 子育て期:家族時間>スキル・年収
ワークライフバランスの考え方
反感を買う可能性があることを承知の上で言いますが、常に五分五分である必要はないと思っています。
私のキャリアでの変遷:
- 新卒〜社会人5年目:ワーク10割(ワーカーホリック時代)
- 結婚・第一子誕生:プライベート10割(長期育休取得)
- 育休復帰後:プライベート7割(休日・業務後の勉強ほぼゼロ、残業無し)
- 現在(5社目):ワーク5:プライベート5(理想的なバランス)
ライフステージに合わせて偏る時期があっても良い
五分五分を維持しようとするより、その時々のライフステージに合わせて、どちらかに偏る時期があったり、五分五分の時期があったりする方が自然だと感じています。
💡 ワーカーホリック時代の詳細
当時の働き方や価値観の変化については、嫌われる勇気レビューの記事で触れています。このテーマはまた別記事で深掘りする予定です。
家族への配慮ポイント
転職時にチェックすべき項目:
- リモートワークの割合:週に何日出社が必要か
- 通勤時間:オフィス出社時の負担
- 出張頻度:家族と離れる時間はどのくらいか
- 残業時間:実際の労働時間はどうか
- 育休・介護休暇制度:制度の充実度と取得実績
私が現職を選んだ理由:
- リモートワーク8割(家族時間の確保)
- AI活用に積極的(スキル習得の可能性)
- CX部署の立ち上げ期(貴重な経験)
- 部署横断のコラボレーション(キャリアの幅)
5社経験して分かったこと
キャリア形成の戦略
1社目→2社目:プログラマー/SE→コンサル転身
- 上流SEとしての経験を積み、コンサル業界へ
- ITスキルとビジネススキルの融合
2社目→3社目:CX内での経験領域拡大
- CXの中でも経験できない領域が出現
- グループ会社との関係性や、ニッチな業界・業務への特定領域の専門知識が多い
- より幅広いCX経験を求めて転職
3社目→4社目:CX以外の領域への挑戦
- 「CXしかできない人」から脱却
- セキュリティなど多様な経験を積む
- CX以外をやってみたら楽しいかも?という期待
4社目→5社目:CX回帰+AI活用の深化
- CX以外の経験を積んだ結果「やはりCXが好き」と再確認
- LinkedInやエージェントからのオファーの質が変化
- AI活用を進めるCXコンサル企業を選択
戦略的なキャリア形成の結果
得られた価値:
- 「CXしかできない人」→「CX+多領域対応可能な人」へ
求人の幅が劇的に拡大 - LinkedInやエージェントからのオファーの質が変化
「CXが弱いが他は強い企業」からのオファー増加
※CX以外も分かる人がCXを推進してくれることを求めていたようです。 - 部署横断・コラボレーション案件の打診
両方を理解している人材として評価 - 自分の適性の再確認
いろいろ経験した結果「やはりCXが好き」と確信
現職で得られたもの
AI活用の実践的知見:
- 社内でのAI推進の取り組み
- AIマーケティングオファリングの構築
- 社内向けAIサービスの開発(少数のエンジニアが構築)
- 顧客への提案と社内実践の両立
立ち上げ期の部署運営経験:
- CX部署の立ち上げに参画
- 部署の方向性策定に関与
- 組織構築の経験
失ったもの(ほぼなし)
リモート比率の若干の減少:
世の中的にコロナも終わり、対面打合せが増えた影響で、若干リモート比率が下がった気がします。ただし、前職でも同じ傾向だったかもしれません。
現状:
リモートワーク8割なので、特に不満はない状況です。
💡 5社経験して学んだ教訓
戦略的にキャリアを形成することで、「専門性の深化」と「対応領域の拡大」を両立できます。ただし、すべてを計画通りに進める必要はなく、その時々で「これが楽しそう」と思える選択をすることも大切です。
★総合評価
| 評価項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 実用性 | ★★★★★ | 転職活動の習慣化は誰でも実践可能で、即座に効果を実感できる |
| リスク管理効果 | ★★★★★ | 突然のリストラや会社倒産に対する備えとして非常に有効 |
| キャリア形成効果 | ★★★★★ | 市場価値を把握し、スキルの方向性を間違えない判断ができる |
| 時間対効果 | ★★★★☆ | 半年に1回1時間程度の面談で、膨大な市場情報が得られる |
| コストパフォーマンス | ★★★★★ | 転職エージェントは無料で利用でき、費用対効果は抜群 |
| 家族との両立 | ★★★★★ | リモート面談が可能で、家族時間を犠牲にせず実践できる |
総合評価:★★★★★(4.8/5.0)
転職する・しないに関わらず、定期的な転職活動(市場価値チェック)はすべての社会人が実践すべき「キャリア自衛策」です。
まとめ
この記事の3つのポイント
1. 転職活動は「転職するため」だけではない
市場価値の定期健診として、転職する予定がなくても継続的に実施することで、突然のリストラやキャリアの危機から身を守ることができます。
2. エージェントとの定期面談で得られる情報は貴重
- 自分の市場価値(年収レンジ)
- 世の中で求められているスキル
- 今の会社で習得可能なスキルの見極め
これらの情報は、キャリア形成の方向性を決める上で非常に重要です。
3. 新卒2年目から始めるのがベスト
「転職する可能性低いし、申し訳ない」と思う必要はありません。エージェントにとっても、将来的な転職候補者として価値があります。
ITコンサルとして大切にしていること
5社を経験してきた中で学んだ最も重要なことは、「社内スキル」と「ポータブルスキル」のバランスです。
どちらか一方に偏るのではなく、社内で必要なスキルを磨きながら、常に「このスキルは他社でも通用するか?」と自問することが大切だと感じています。
そして、その判断材料を得るために、転職活動(市場価値チェック)を習慣化することが、大手リストラ時代を生き抜くための最も確実な「キャリア自衛策」だと確信しています。
一緒に、予期せぬキャリアの危機から身を守る準備をしていきましょう!
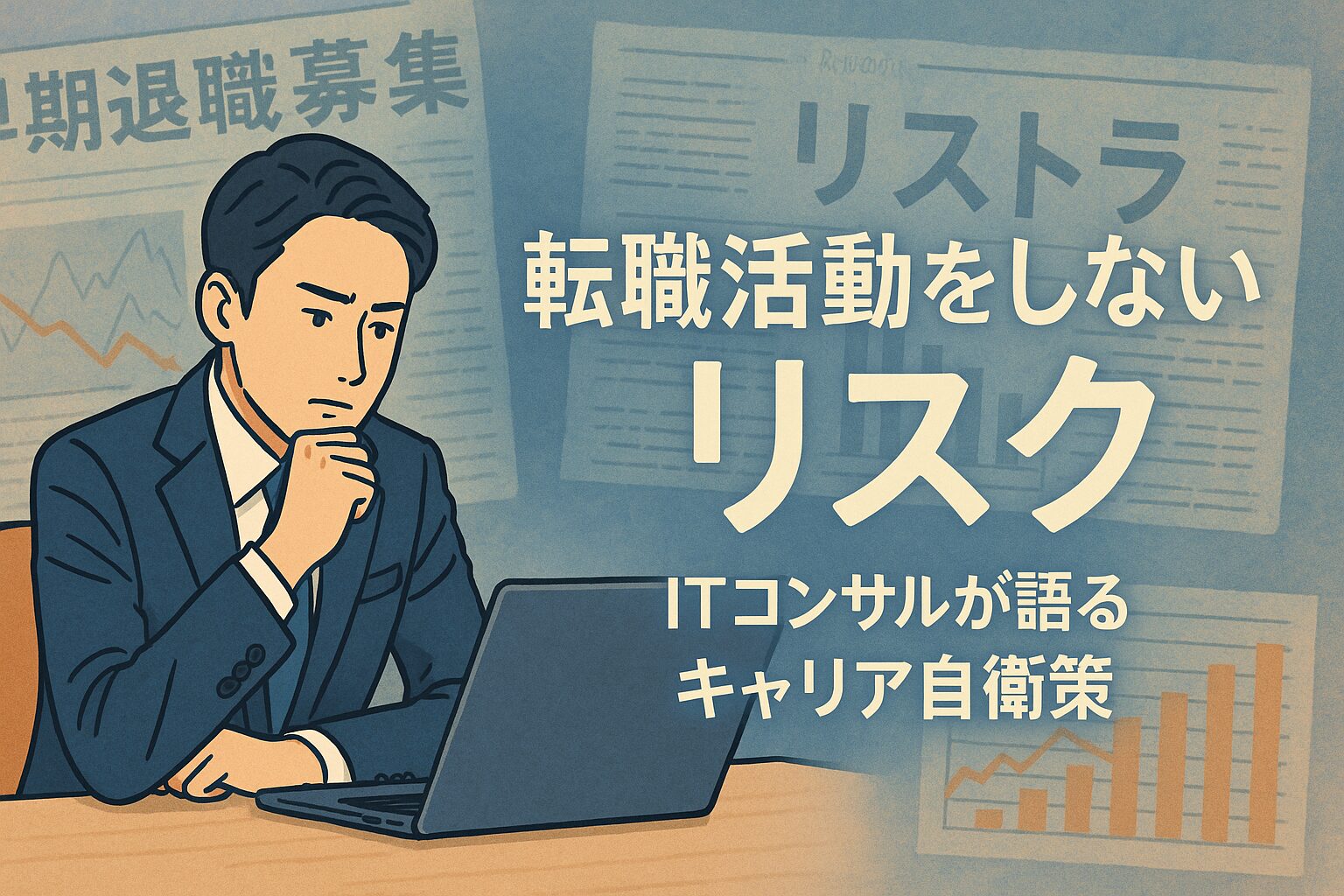


コメント